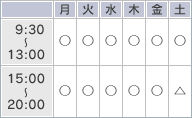[ 2013.11.30(土) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
2013年も残すところあと1ヶ月。今年もあちこちでXmas Illuminationが点灯し始めました。
まこと歯科クリニックも、毎年恒例になりましたXmas Illumination。
今年も気が早く、11月初旬に飾り付け、既に華やかに点灯しております。
今年、初登場したのは、医院の入口ポストの下に置かれたLEDのSanta Claus。
楽しそうにラッパを持ったSanta Clausの合図で、医院のIlluminationが点灯する・・・
そんなイメージ(^J^)
あとは診療室の窓に飾られた、プレゼントの貨車を引く汽車と“Merry Christmas”と書かれたLEDのパネル。どちらも可愛らしいです。
毎年スタッフと私がセレクトして飾り付けをし、今年もXmas mode一色です。
皆様も忙しくなる年末ですが、今年最後の歯のお手入れもお忘れなく!
院長。。

[ 2013.11.29(金) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
前回のブログの続きです。
前回でも紹介したように、親御さんがお子様の歯並びを気にされる時期は、下顎の前歯が萌える時期と「みにくいアヒルの子の時期」が多いように感じます。
歯並びが自然に改善されることが最も理想的です。しかし、どう診ても歯の萌えるスペースが不足していたり、顎が小さかったり、歯が大きかったり、乳歯の虫歯が多く歯の崩壊が進んでいたりなど、様々なリスクがあると自然治癒の期待が薄れます。
そんな時は歯並びを治す矯正治療を勧めます。
では、お子様の矯正治療はいつ行えばいいのか?
矯正治療は歯の表面にブラケットを付け、ワイヤーなどで歯を移動したり固定したりするのがオーソドックスですが、最近では歯の裏側にブラケットを付ける舌側矯正や、取り外しが可能な床矯正、マウスピース矯正など様々な矯正のテクニックがあります。
私自身も矯正治療を行っておりますが、私のテクニックで書かせて頂くと、
まず、上下顎前歯と第一大臼歯が萌出し、咬み合せの三点接触ができたら始めます。
ただし、萌出スペースが不足していたり、咬み合せが反対だったり、成長に任せて自然治癒が期待できない場合に行います。
矯正する際には必ず、規格化された正面と横のレントゲンおよび、手根骨を撮影するとともに、歯の大きさ、上下顎歯槽骨の長さと幅を計測・分析し、成長予測をたて診断してから行うのが鉄則です。
診断した結果、成長に任せながら治していくのか、成長を抑制して治すのか、スペースを得るために歯を抜かなくてはならないかなど治療計画をたてます。
もし放っておいたらどうなるか・・・?
歯並びの治療ですから、虫歯や歯周病がなければいつでもできます。
お子様の場合は、本人がやる気ならば治療をしますが、親御さんが無理に勧める場合は考え直して頂くことがあります。
今回、「歯の萌え変わりと歯並び」について書かせて頂きました。
参考になって頂ければ幸いです。また、相談も受け付けております。
院長。。
[ 2013.11.27(水) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
秋は歯科検診の時期でもあり、連日検診希望でお見えになられる方が増えているように思えます。
なかでも、お子様の歯の萌え変わりや、歯並びを気にされる親御さんも多く、
年齢的な歯の萌え変わりを、歯槽骨の成長と関連させて説明したいと思います。
まずは下顎切歯が6〜7歳で萌え変わるとともに、乳歯列最後方部に上下顎第一大臼歯が萌えます。
その後上顎切歯が7〜8歳で萌え変わり、その後下顎側切歯、上顎側切歯と萌え変わります。
その時に、よく相談されるのが上顎の前歯が扇状に萌え隙間があること(正中離開)と、下顎の前歯が舌側に萌えてることです。
下顎の前歯はもともとエスカレーターのように萌えるため、舌の圧力で前方に移動し自然に改善されます。
上顎の前歯のこの時期を、我々は「みにくいアヒルの子の時期」(Ugly Ducking Stage)と呼んでおりますが歯並びが開いているのは一時的なもので、いずれ正常でまっすぐな歯並びになることを期待します。
この時期は、乳歯と永久歯が混ざった混合歯列なので、しっかり歯磨きをしないと虫歯や歯肉炎になりやすい時期です。
そして9〜12歳にかけて、上下顎犬歯、第一・第二小臼歯が萌え変わることにより、歯槽骨が側方へ拡大成長し、乳歯と永久歯の幅の差により「みにくいアヒルの子の時期」の改善が期待されます。
その後11〜14歳で上下顎第二大臼歯が萌え、歯槽骨が後方へ成長します。
歯の萌え変わりの年齢はあくまでも平均であり、その前後であっても珍しくありません。
「他の子は萌え変わっているのに、うちの子はまだ・・・」という心配も、レントゲンを撮影すれば、永久歯が存在していることの確認ができます。
それでは、いつ歯並びを治せばいいのか?次回のブログで紹介したいと思います。
院長。。
[ 2013.11.21(木) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今日、開院当初よりお世話になっております税理士事務所の所長さんから素敵なシーサーの置物を頂きました。
シーサーは、沖縄県などでみられる伝説の獣の像で、建物の門や屋根、村落の高台などに据え付けられ、家や人、村に災いをもたらす悪霊を追い払う「魔除け」の意味を持ちます。
名前は「獅子」を沖縄方言で発音したものです。
スフィンクスや中国の石獅、日本本土の狛犬などと同じく、源流は古代オリエントのライオンもしくは犬と伝えられております。
元々は単体で置かれていたそうですが、狛犬の様式の影響を受けて、阿吽像一対で置かれることが多くなったそうです。阿吽の違いにより雌雄の別があり、口の開いたシーサーが雄で、右側に置き、福を招き入れ、口を閉じたシーサーが雌で、左側に置き、あらゆる災難を家に入れないとされているそうです。(Wikipedia参照)
早速、受付に飾らせて頂きました(^O^)/
なかなか可愛いシーサーですねぇ\(^o^)/
院長。。

[ 2013.11.15(金) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
皆様、秋はどこにいっちゃった? 既に冬・・・?
というぐらい、寒くなりましたがいかがお過ごしでしょうか?
空気が澄みきっているためか、夕焼けが見事なこと。
(最近、夕焼けをテーマにした写真やブログが多いかも(笑))
今日は水色の空に、夕陽を浴びたピンク色の雲が浮かび、オレンジ・水色・ピンクといった感じに調和した、パステルカラーの見事な夕焼けを見せてくれました。
診療中とはいえ数分の出来事に目を奪われ、またもや診療の合間に外に出てパシャリッ!!
素敵な夕焼けでした。
冷え込みも日に日に増し、また、乾燥もしてきました。
皆様、手洗いウガイをしっかり行い、体調管理をしっかりしていきましょうね。
院長。。

[ 2013.11.12(火) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
先日、我が家はスカイツリーに行って参りました。勿論、初めてです!
秋晴れで爽やかな陽気。しかも快晴に恵まれ、ちょうど夕方に展望台に昇ったため夕陽が見事でした。
東京スカイツリーは、全高(尖塔高)634m、軒高(塔本体の屋上の高さ)497mで2012年完成時点の自立式鉄塔としてはキエフテレビタワーの385mを上回る世界第1位。現存する電波塔としてはKVLY-TV塔の628.8mを上回る世界第1位。
2011年11月17日に世界一高いタワーとしてギネス世界記録の認定を受けました。人工の建造物としてはブルジュ・ハリーファの828mに次ぐ世界第2位となります。
エレベーターも地上4階から350mの高さにある第1展望台まで約50秒間。分速にすると600m。第1展望台と450mの高さにある第2展望台までは約40秒間で分速240m。昇降距離が464.4mと日本最長です。
第1展望台を天望デッキ、第2展望台を天望回廊と名付けられ、そこからの眺めも最高でした。
エレベーター内のデザインもそれぞれあるらしく、たまたま行きも帰りも同じ江戸切子の装飾がされており、素晴らしく華やかでした。
まだ行かれてない方も、すでに行かれた方も、これからの季節。晴れた日の眺望は最高だと思いますので、是非足を運ばれてみてはいかがですか?
ちなみに、非常階段数は2523段(地上1階から天望回廊上の業務フロア458mまでの数)だそうです。
院長。。

[ 2013.11.8(金) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
皆様、本日11月8日は何の日かお解りですか?
『日本歯科医師会は、「いつまでも美味しく、そして、楽しく食事をとるために、口の中の健康を保っていただきたい」という願いを込め、厚生労働省とともに1989年(平成元年)より「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という「8020運動」を積極的に推進しています。
そして1993年(平成5年)に、11月8日を「い(1)い(1)歯(8)」の語呂合わせで設定しました。「いい歯の日」は、その「8020運動」推進の一環であり、国民への歯科保健啓発の強化を目的としています。』
ということで、正解は「いい歯の日」でした。
皆様、ご存知でしたか?
「いい歯の日」も笑顔であって欲しい!
まこと歯科クリニックも、スタッフ一同全力で、皆様のお口の健康維持・管理を頑張っておりますので宜しくお願い致します。
院長。。

[ 2013.11.1(金) ]
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今日、患者様より「親知らずから新しい歯が出来ちゃうんだって!?」
と言う質問があり、私も気になり、すぐに調べてみました。
「なるほど!iPS細胞(ヒト人工多能性幹細胞)のことをいっているのか!」
人体のあらゆる組織に成長できるiPS細胞ですが、2009年に開催された日本再生医療学会で、抜歯した親知らずに含まれる細胞に、従来より少ない2つの遺伝子を組み込み新型万能細胞であるiPS細胞を作製する事に成功したと岐阜大より報告されております。
親知らずに含まれる歯髄幹細胞では、iPS細胞作製に必要な4遺伝子のうち2遺伝子がもともと働いていることに着目。残り2遺伝子を組み込むと、効率は非常に低いがiPS細胞ができたとのこと。
3遺伝子を組み込むと、皮膚細胞からiPS細胞をつくる方法に比べ、作製効率は最大で約40倍になった。通常、親知らずは抜歯後に捨てられるため入手しやすく、研究チームは「iPS細胞の有力な材料になる」としているとありました。
2012年、生物のあらゆる細胞に成長できて再生医療の実現につながるiPS細胞を初めて作製したとして、ノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授が脚光を浴び、一躍有名になったiPS細胞。早く臨床の場に登場して欲しいですね。
「はい。今日は歯の無い所にiPS細胞を埋めますね。」なんて時代が、近い未来に来るのでは・・・?
と、患者様には答えました(笑)。
院長。。